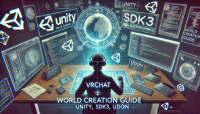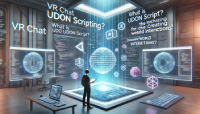![h2]()

VRChatは2017年頃までは「知る人ぞ知る」コミュニティでした。しかし、その名前を世界中に広めたきっかけが、Ugandan Knuckles(ウガンダナックルズ)と呼ばれるミーム現象です。
・元ネタ:人気ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』シリーズのキャラクター「Knuckles」を、デフォルメして描いたファンアート。もともとはYouTubeのパロディ動画から広まったものです。
・VRChatでの爆発的流行:このアバターを使ったユーザーがVRChatに集まり、特有のフレーズ(「Do you know de way?」など)を繰り返しながら群れを成して行動しました。
・結果:ゲーム実況者やストリーマーが次々とこの様子を配信し、VRChatが一気に「ネットで一番カオスな場所」として拡散されたのです。
VRChatは本来、ユーザーが自由にアバターやワールドを制作し、遊べる「UGC型プラットフォーム」です。その中で「ミーム文化」が重要な役割を果たしました。
1.アバターの自由度
誰でも好きなキャラクターを作り、共有できるため、ミームの“物理的な具現化”が容易。
2.同時接続とカオス感
大人数が同じアバターを使い、同じフレーズを連呼することで「ネット文化の祭典」のような空気が生まれました。
3.配信文化との相性
TwitchやYouTubeでの実況配信がバズを拡散。視聴者は「自分もやってみたい」と参加し、さらにユーザーが増える循環に。
・一目でわかるインパクト:見た目のユーモアと集団行動のシュールさが、誰でも笑える要素だった。
・バイラル要素:フレーズの真似、動画編集のしやすさ、アバター配布の簡単さが、SNS時代に合致。
・文化的ハブとしての自覚:VRChat運営も「UGCとミームがユーザーを惹きつける」という強みを再確認し、プラットフォーム方針に影響を与えました。
もちろんUgandan Knuckles現象は「差別的」「不快」と受け取る声もあり、コミュニティ規約やモデレーション強化の契機にもなりました。
つまり、人気の拡大と同時に「秩序をどう保つか」という課題を突きつけた事件でもあったのです。
・「Ugandan Knuckles」で一躍有名になった後も、VRChatでは次々とミームが誕生しました。
・例:巨大化したキャラクター、楽器演奏ワールド、リズムネタなど。
・この文化は「ユーザーが遊びを作り、それが配信・SNSで拡散して人を呼ぶ」というUGCプラットフォームならではの成長モデルを確立しました。
・VRChatが世界的に注目を集めた最初の大きなきっかけはUgandan Knuckles現象。
・「自由に作れるアバター」「ミーム文化の拡散」「配信との相性」がブームを作った。
・同時に、コミュニティ健全化の課題も浮き彫りになった。
・今でも「ミーム文化」はVRChatのユニークさを象徴する要素であり、新しい波を次々と生み出し続けている。